
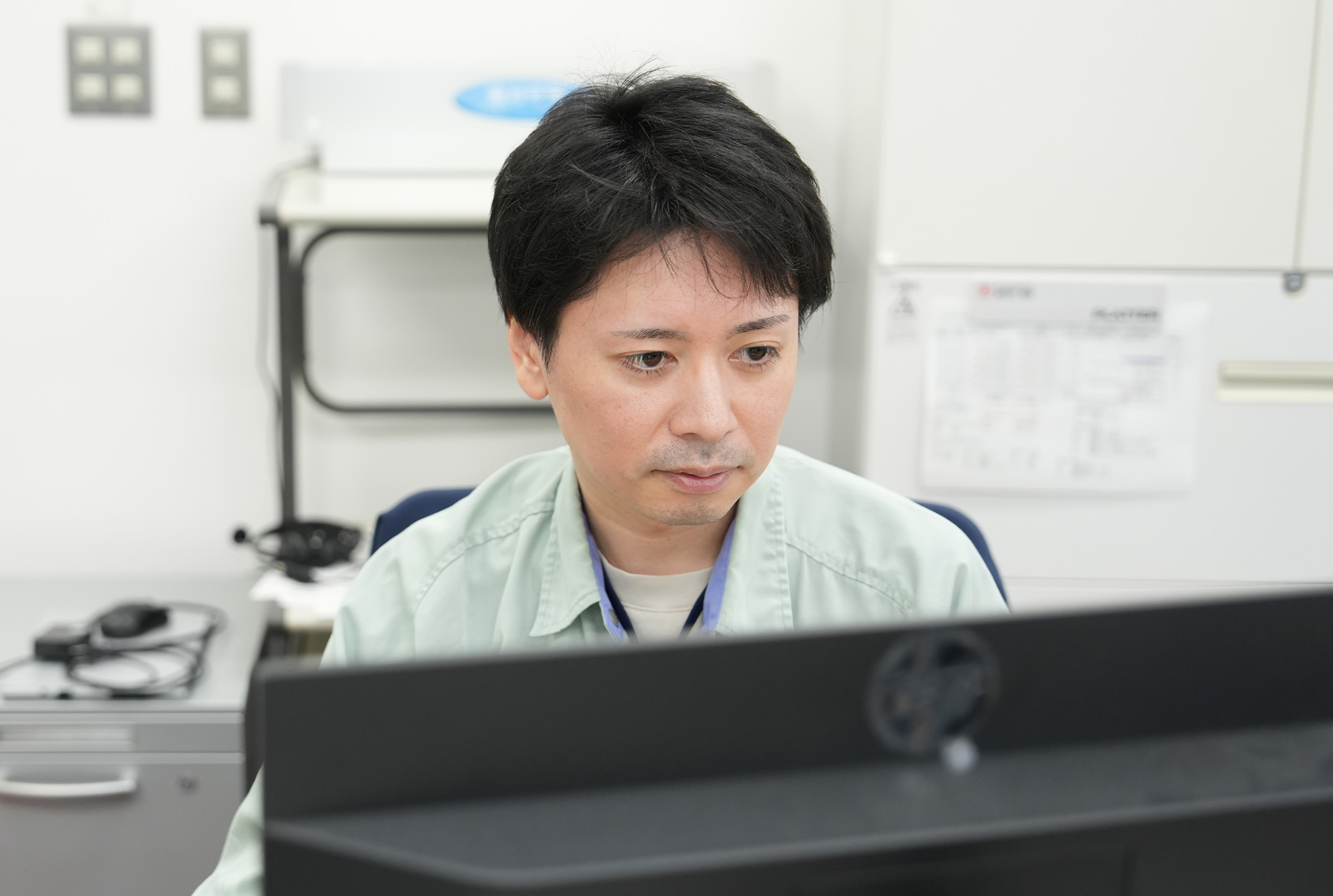
私は情報工学出身で、化学の素養はありませんでした。それが直接的な理由かは分かりませんが、入社後の研修期間が長くて、技術グループで2年、製造グループで1年、計3年間みっちりと鍛えられました。社員の中で一番長い研修を受けたのは私です。当時、毛色の違った新入社員をどう育てたらいいか、会社も試行錯誤していたのかもしれません。 ちなみに、化学専攻の後輩の研修は数ヵ月でした(笑)。
旭工場での製品製造は、まず2ℓのフラスコで試作し、次に200ℓのパイロット釜で試製造し、最終的に1000ℓの反応釜で製品化しますが、この間の原料から製造工程、設備にわたっての管理までを担当しています。試作品を最終段階までスケールアップしていく際に、同じ品質を維持するように見守る、いわばゲートキーパー的な存在ですね。
「デザインレビュー」というものを行っています。これは、パイロット製造の結果を報告するもので、それを元に「生産技術会議」を開きます。ここで課題を洗い出し、どう解決するかを話し合います。これは当社の特徴でもありますが、生産技術会議には営業も多数参加します。営業だから技術は分からないということはなく、バンバン意見が飛び交います。営業の意見が反映されることが、お客様に寄り添ったご提案や、課題解決に向けた取り組みに繋がっていると思います。
製造工程のシステム化を進めたことです。製造工程は既に自動化されていたのですが、古いシステムでした。これを新しく再構築する際にプロジェクトリーダーを務めました。といっても全部で3人のプロジェクトですが(笑)改良点としては、グラフィックで工程が一目で分かるようにしたこと。今どのバルブが開いていて、液がどのように流れているかなどを見える化しました。またインターロックを強化し、ある動作を終えてからでないと次の動作が出来ないようプログラムして、誤操作を防ぐ仕組みを作りました。

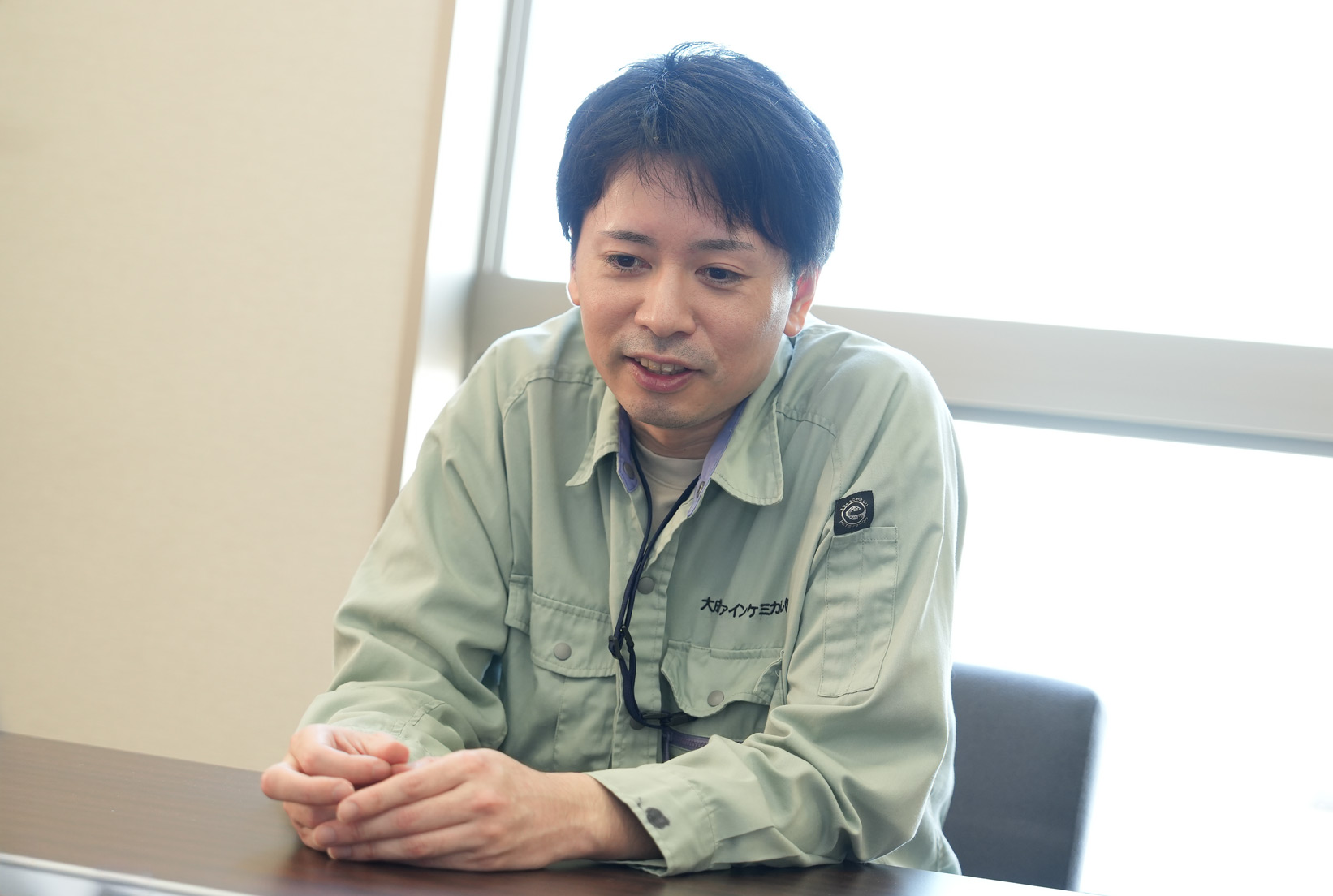
もう何年も前ですが、新小岩の本社にあったパイロットプラント*が旭工場に移設した時に、チームを組んで新プラントの運用ルールを一から作りました。実例も何もない中、営業から依頼を受ける→ 技術グループが設計書を作る→ 生産技術グループが指図書を書く→ それを元に原料を計量して実際に製造し→ 充填する、という一連の流れをスムーズに回していくための運用ルールを作り上げましたが、これはなかなか大変な仕事でした。当時は営業からの依頼一覧などはエクセル文書だったのですが、今はデータベースを利用して、自動的に通知が来てすぐにアクセスできるシステムを整えています。
もともと生産技術は守備範囲が広いこともありますが、確かに他の部署からよく声をかけられます。私のような元システム系の人間は、使い勝手がいいのかもしれません(笑)今もまた、ある部署から効率化、システム化の依頼が来ているところです。
最終製品を作る大型の反応釜についてはシステム化できたので、次はパイロット釜*のシステムを再構築したいですね。現在一部は自動化されていますが、システムにまだ改善の余地があるかな、と…。これを、温度や滴下速度などを自動的に、正確にコントロールできるようにして、誤差やミスを予防できるシステムを作っていきたいと思っています。
*)パイロットプラント・パイロット釜:新製品などを実際に量産する前に、試験的に生産を行うプラントや設備を指します。化学を知らない異色の社員として15年。言えることは、「違うからこそ面白い」ということです。化学の知識は入社してからでも十分学べます。不安は不要ですよ!